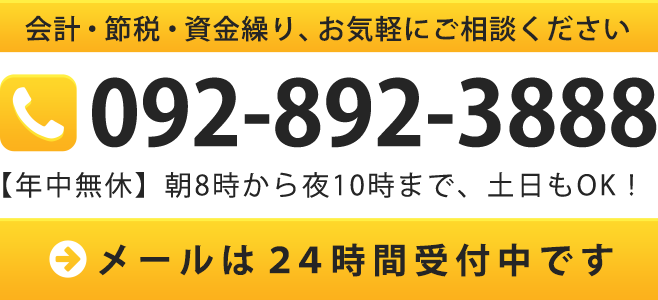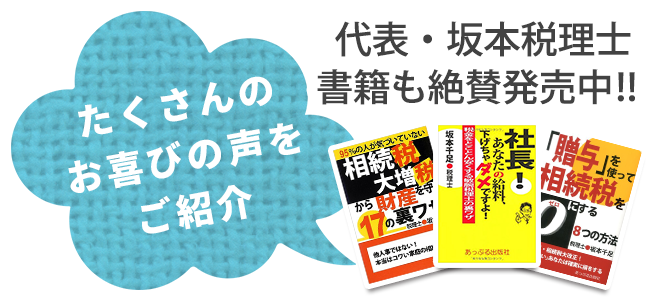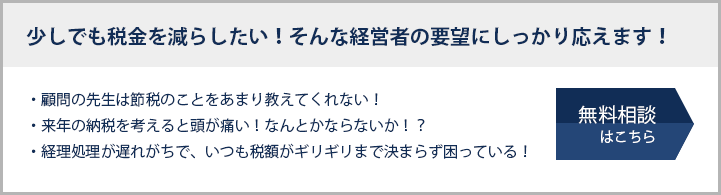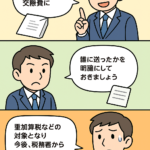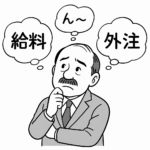節税と社宅家賃~「小規模住宅」面積99㎡の計算方法
2022年02月16日
節税ブログ その92
●節税と社宅家賃~「小規模住宅」面積99㎡の計算方法
■税法上のメリットを受けるために必要な面積要件
借上げ社宅を利用した節税方法については、このブログでも詳しく書いています。
会社が負担する社宅家賃は会社の経費に計上することができますが、そのためには、そこに住む社長や社員から一定の賃料を徴収することが条件となっています。
問題は、その自己負担分をいくらにしたらよいか―ですが、税務上の有利な取り扱いを受けるためには、役員の場合、非木造家屋(つまりマンション等)の場合、床面積が
99㎡以下
であることが条件となります。
ところが、その面積の判定については税務の解説書やネット上の記事で
マンション等では共用部分も含めて判定しなければならない
といった記載があるのをよく目にします。
■面積99㎡以下はどう計算するべきか
さて、適正な個人負担分を計算するための算式は、実は、法律ではなく、お役所が実務的な取り扱いをする際の指針となる「通達」に詳しく書いてありますが、その通達自体には、共用部分を含めなければならないといったことは、実は、何も書いてありません。
ただ、通達に関しては「逐条解説(ちくじょうかいせつ)」といって、我々税理士などの専門家が参考にする専門書があって、その解説に
専用部分の床面積だけでなく、共用部分の床面積についても、使用部分を適宜見積もって含める必要がある
と書いてあるだけなのです。
他の書籍やネット上の記事にある「共有部分も含めて判定」する旨の文章はその逐条解説を参考にしたと思われます。
ところで、マンションは
・専有部分 住戸部分
・共用部分 バルコニー、玄関扉、駐車場等々、専有部分以外の一切
のふたつからなります。しかし、バルコニーが共用部分というのは、多くの方が意外に思われるかもしれませんね。
というのも、バルコニーは通常、洗濯物を干したり、植木を置いたりと、入居者が個人的、独占的に使用することがほとんどですから、どうしても、専有部分という様に思われるのも仕方がないことですね。
ところが、実際は、火災などが起こった際にマンション住民が退避のために使用するものとしてバルコニーは共用部分に含まれるわけです。
■共用部分のうちの使用部分とは
そこで、マンションの面積の話にもどりますが、先ほどの逐条解説は
専用部分の床面積だけでなく、共用部分の床面積についても、使用部分を適宜見積もって含める必要がある
となっていますから、共用部分であっても、専用的に使用している部分は、やはり、適宜見積もって居住スペースの面積にプラスする必要があるということになります。
では、共用部分であっても、専用的に使用している床面積は何かというと、私は
バルコニーの部分
ということになるんだろうと思います。
ただし、通常、不動産関係のポータルサイトを見ても、バルコニーの面積というのは書いてありません
ちなみに、公正競争規約では区分所有建物の場合は専有面積を表示することとされています。
ですから、そこは、バルコニーの面積は、まさに適宜見積もって居住スペースにプラスしたうえで、先ほどから申し上げている99㎡以下かどうかの判断をすることになると思います。
注)以上お話ししたことは、あくまで私の個人的見解であって、税法等に示された方法ではないことを念のため申し上げます。
社宅の面積判定について詳しくお話をお聞きになりたいと思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
| 前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |