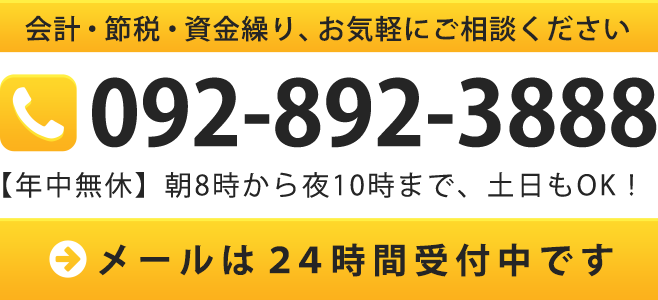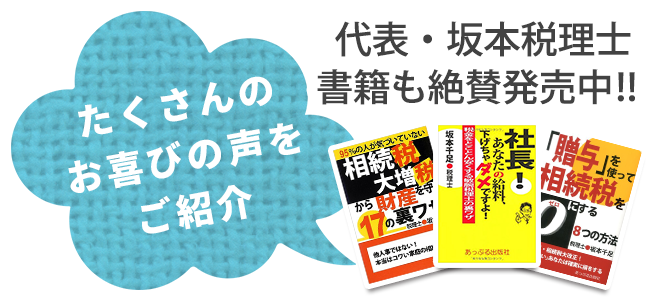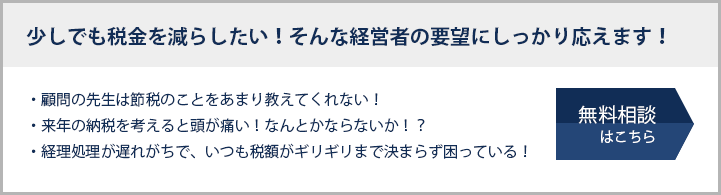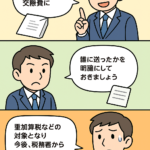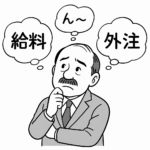節税と税務調査~税務調査でよく見られる4つのポイント
2025年03月11日
節税ブログ その129
●節税と税務調査~税務調査でよく見られる4つのポイント
■ 税務調査って何を聞かれるの?何を見られるの?
「節税はしたいけど、その後でもし、税務調査なんかに来られたらいやだしなぁ・・・」
なんて思われる会社社長や個人事業主の方は多いかもしれませんね。
確かに、税務調査はいつ入られるかわかりませんし、同業者仲間から「あそこの会社、調査で〇〇万円持っていかれたらしいよ」なんて聞かされたりしたらなおさらですね。
それだけに、日頃からルールにのっとった正しい経理処理や対策を心がけておくことが必要なんですが、では、実際の税務調査では、どのようなポイントが重点的にチェックされるのでしょうか?
調査は通常2日~3日程度かけて行われ、調査官は会社や事業所に出向いて帳簿等を見た後は、必要な資料を税務署に持ち帰ってこれを検討します。調査官には年間の調査ノルマがあるので、どうしても限られた時間内に効率的に処理する必要があるというわけです。
なので、税務調査では特に「金額が大きく、まちがいがあればすぐに税金が取れる」項目が重点的にチェックされます。
その項目とは次の4つです。
■税務調査でよく見られる4つのポイント
・売上
・原価
・人件費
・特別損益
先ずは、売上と原価(売上原価と製造原価)です。
会社でも個人事業でも、売上や原価は一個一個の金額は比較的大きいですから、その売上がもれていたり、逆に仕入が過大に計上されていたりしたら、調査官から
あぁ、これは直していただかなきゃいけませんねぇ・・・
となって、税金ゴソっと持っていかれるってことになります。
しかし、「売上」とひとことで言っても、実際はどの時点で上げるべきなのかで、その期の売上は大きく変わってしまうことがあります。
■売上計上基準は何を選ぶ
たとえば、商品の「注文」を受けた時点で売上を計上するのか、あるいは、その商品を「発送」した時点で上げるのか、相手に「引き渡した」時点なのか、相手がその商品を「検収」した時点なのかによって、その年の売上は大きく違ってきます。
売上計上基準は業種や業態によって違ってきますし、同じ会社でも違う種類の商品を扱っていれば、商品ごとに異なる売上計上基準を選ぶ必要だってあるかもしれません。
だから、どの「売上基準」を選ぶかはとても重要です。商品を相手に引き渡したら終わりではなくて、相手が一度その商品をチェックしてみて「うん、これなら大丈夫!」と言われて初めて売上に計上する―ということが必要な場合だってあります。
そうすると、決算月の終わりに商品はお客様が受け取っていたけれど、チェックが行われたのは翌期に入ってからだったという場合は、決算でその商品は売上に上げる必要はなかったということになります。
もっとも、その時は仕入れの方も、期末棚卸しにあげて原価から外しておく必要があります。ちなみに一度決めた売上計上基準は継続して適用するのが原則です。
そういう意味で、特に決算月は売上、仕入ともに注意を払っておかなければいけません。
その点を間違ってその月に売上に上げなきゃいけなかったものを上げていなかったのが調査で見つかったら、残念ながら言い訳はできません。
「いやぁ、翌月には売上にはあげているわけだし、2年間で通算したら一緒なんだからいいじゃないか」っていう言い訳は残念ながら聞いてもらえません。
その年に処理すべきものはその年に処理してくださいねーって言うのが税務の基本的な考え方だからです。
■人件費~親族に対する給与は特に要注意!
人件費も税務調査で重点的にチェックされる項目です。特に、法人や個人を問わず
親族に対する給与
は要注意です。
例えば、会社社長の奥さんや両親、子どもに給与を支払っている場合は税務調査では次の点が細かく見られます。
・実際に働いているかどうか
・具体的にどんな仕事をしているか?
・支払った給与が仕事の内容に対して適正かどうか?
最後の支払った給与が適正かどうかというのは、もちろん、大変大事なポイントですが、案外、これが問題になることは少ないです。
■金額よりも仕事の実態はどうなのか
なぜかというと、税務署は具体的に「適正額は〇〇万円です」というのを出さしたうえでないと、納税者側が計上した金額を否認できないからです。
じゃあ、それはどうやって出すのか―というと同業種・同規模の法人で、同じような仕事をしている人に支払われている給与の額をいくつかさがして来て、これを検討したうえで納税者に示さなきゃいけません。ですから大変です。正直、税務署としてはあまりやりたがりません。
しかし、家族が「名前だけ従業員」になっていて、実際には働いていないのに給与が支払らわれていたり、仕事はカタチだけで、実質的にほとんど何もしていないといったケースでは、こちらは否認されてしまいます。架空人件費だからです。
社長の給料の一部を奥さんの給料として支給するのは「所得の分散」といって、節税になりますが、上に書いたような点は十分に気をつけるべきなのです。
■特別損益も要注意
特別損益というのは臨時的に発生する利益や損失で、損失の方だと貸倒れ損失や役員退職金がありますが、これらも税務上、やはり注目されます。
もちろん、臨時的なものですからで毎年あるわけじゃありませんが、発生するときは金額は大きくなる可能性が高いですから、やはり要注意です。
特に役員退職金は長い期間かけて計画的に対策を実行してきた結果、支給されることが多いですから、最後の最後で否認されたりしたら大変です。
くれぐれも注意してください。
節税はしたいけど、税務調査が心配だという経営者の方は
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
| 前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |