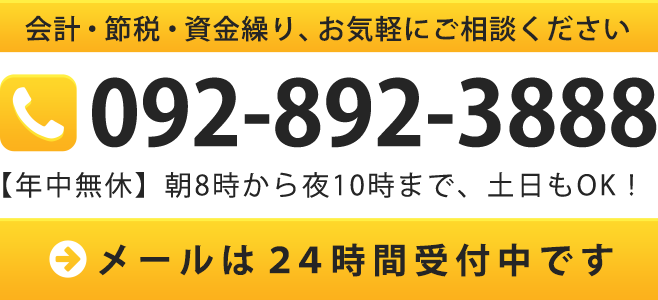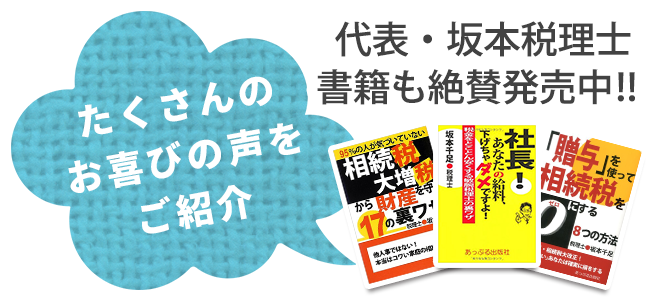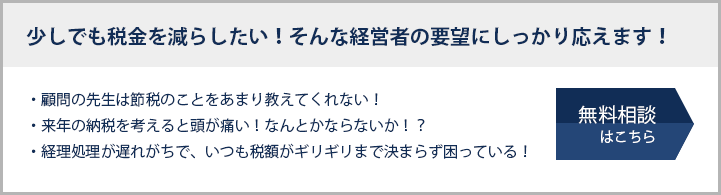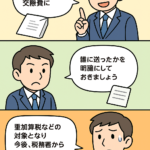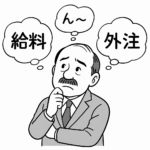節税と外注費~給与か外注費か-の判断と税務上の取扱い
2024年11月25日
節税ブログ その125
●節税と外注費~給与か外注費か-の判断と税務上の取扱い
■給与と外注費の区別は本当はむずかしい
会社の業務を行う場合に
・社員にやらせる場合
・外部の業者に委託する場合
のふたつのケースがあります。
前者は雇用契約、後者は請負契約です。雇用と請負で違いはハッキリとしていそうですが、実際は、その区別がなかなかつきにくい場合も多くあります。
■4つの判断基準
給与か外注費かの区別は、一義的には、契約書の内容に基づきますが、契約書を取り交わさない場合だってありますから、そうなると大事なのは実際の業務の中身で判断されるということになります。
そして、その判断基準としては一般に次の4つの規準があげられます。
1.業務の内容が他人の代替を容認するかどうか
2.業務の実行に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
3.仮に業務の結果が依頼した側の期待通りでなかった場合でも、それに対する支払いがなされるかどうか
4.業務の実行に当たり必要な材料や用具などが与えられているかどうか
■判断は総合判断
1の他人の代替を容認する-というのは、要は身代わりがきくかどうかということです。たとえば、会社員の場合だと、朝起きて具合が悪いからといって、自分の友人を代わりに会社に行かせるというわけにはいきません。
その点、請負(外注費)だと、同業者の誰かに代わりに行ってもらうということはあり得ない話ではありません。これが他人の代替が容認されるという意味です。
2の指揮監督を受けるというのは、会社員を考えればわかりますね。基本的には誰かの指揮監督の下で働くのであれば、それは給与という扱いです。
しかし、外注業者の場合であっても元請けの指揮監督のもとで働くということはありえます。ですから、大事なのは、4つの基準のひとつに該当しているから、それだけで外注費だ、給与だと判断されるというわけではなく、あくまで4つの基準をひっくるめて総合的に判断することが必要だということです。
次の3は仕事が結果的にうまくいかなかった場合のあつかいですね。従業員の場合であればよほどの大失敗でない限り給与は払われます。しかし、外注業者であれば、失敗した分は減額されるか、まったく払われないかどちらかです。こちらははっきりしていますね。
最後の4は仕事に必要な材料や用具が与えられるかどうか。従業員であればそれらは当然、会社等から与えられますから給与ということになりますが、2と同じように、外注業者の場合でも会社が用意した材料などを使って仕事をすることはありえます。だから、「総合判断」なのです。
■4つの判断基準で判断しきれないときは
実務上は以上4つの基準では判断しきれない場合も多々あると思われます。そういう時は平成15年7月に東京国税局の内部資料として出された
「給与所得と事業所得との区分 給与?それとも外注費?」
が参考になります。資料では35もの基準が示されていますが、その中には
・支払者から制服等が支給あるいは貸与されているか
・名刺、名札で支払者に帰属しているようになっているか
といったものもあります。答えがYESであれば給与という事なのですが、これも、たとえば会社側が、外注先であっても一般のお客様から見たときに営業政策上、社員と同様に見える様に制服を支給するということはあるでしょう。
名刺もしかりで、外注先の人間に外注費を支払う側の会社が、その会社の名刺を持たせて営業活動他をしてもらうということもありえます。
他には
・以前にも他の支払者のもとで同様な業務を行っていたか
というのもあります。答えはYESであれば給与ではない、つまりは外注費ということなのですが、これもおもしろい視点ですね。
■給与と外注費で税金と社会保険はどう違ってくるか
さて、次は給与と外注費で税務上の取扱い等がどう違ってくるかというお話です。
先ずは、源泉所得税。
給与の場合は支払いのたびに源泉所得税を徴収しなければいけませんが、外注費の場合はその必要はありません。
社会保険料の負担も違います。
給与として払えば、払う側、もらう側双方に社会保険の負担が生じますが、外注費で支払えば、会社側にその負担はなくなります。
最後が消費税。
消費税の計算は売上に係る消費税から仕入や経費(これをまとめて「課税仕入れ」といいます)に係る消費税を引いて計算されますが、給与は課税仕入れに該当しませんから、結果的に会社が納める消費税はその分増えます。
これがあるから、多くの会社または個人事業者は「給与」をやめて「外注費」に切りかえようとするのです。
つまり、支払う側の会社や個人事業者の立場からみれば、外注費の方が断然有利なのです。
しかし、外注費とされた場合は、これを受け取る側からするとどうでしょうか。
■外注業者となったらどうなるか
先ず、受け取ったのは、給与ではありませんから、事業収入として確定申告をする必要があります。
給与の場合は「給与所得控除」といって、大体、収入の2割~3割が引かれて「給与所得」が計算され、その「所得」を基礎として税金が計算されます。一方、事業収入の場合は、それを得るためにかかった様々な「経費」を差し引いて税金が計算されるのですが、事業の種類によっては外注業者がほとんど経費の負担をすることなく、支払いを受ける場合もあります。
そうなると、受け取った金額がほぼほぼ利益となって、税金の負担が「給与」よりも多く発生してしまうケースだってありえます。これは決して珍しいことではないのです。
また、給与であれば社会保険料は会社がその半分を負担してくれますが、外注費の場合は全額自己負担です。
当然、確定申告も自分でしなければなりません。
会社のメリットを優先するか、働く側のメリットをどこまで考慮するか-いずれにしろ、給与と外注費の問題は経営者にとって頭の痛い問題です。
給与と外注費をうまく使いこなしたい・・・と思ったら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801
――――― お問合せ先は ―――――
TEL092-892-3888/FAX092-892-3889
| 前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |